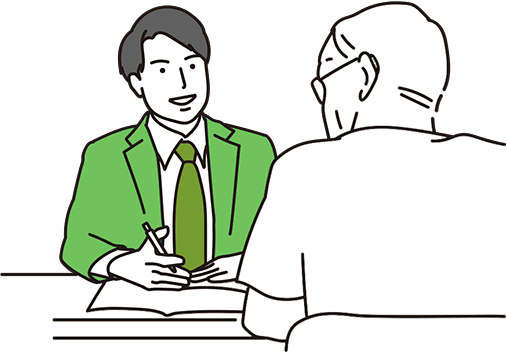2025.03.06
育児時短就業給付金とは?どんな人が利用できる?
今の日本では、少子高齢化による労働力人口の減少を食い止めるため、従業員が育児を理由に退職することのないようにしなければなりません。そのためには、仕事と育児の両立を支援していくことが重要です。
令和7年4月から「育児時短就業給付金」が新設されます。
今回は「育児時短就業給付金」とは何か、どのような人が利用できるのかについて解説していきます。
※内容は現時点でのものです。今後の法改正の内容によって変更になる可能性があります。
「育児時短就業給付金」とは?
「育児時短就業給付金」は雇用保険から支給される給付金です。簡単に言えば、育児短時間勤務制度を利用し勤務時間が短くなったため、毎月の給与が減った人が受けられる給付金です。
3歳未満の子を養育する労働者に対して、育児短時間勤務制度を設けることは企業規模を問わず、企業の義務になっています。
育児短時間勤務制度は、1日の勤務時間を6時間にすることが原則ですが、本人との話し合い等で1日6時間以内とすることも可能です。
育児短時間勤務制度を利用し勤務時間が短くなった場合は、短くなった分の給与を減らすのが一般的です。給与を減らさずに満額支給することも可能ですが、その場合はこの給付金を受けることはできません。
「育児時短就業給付金」の受給資格は?
「育児時短就業給付金」の受給資格は次の2つ要件を両方満たす場合です。
①2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する被保険者であること
※被保険者とは雇用保険の被保険者です。育児短時間勤務制度は3歳未満の子が対象ですが、この給付金については2歳未満の子になっていることに注意する必要があります。
②育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月あること
※育児休業は、子が1歳まで(要件を満たす場合は2歳まで)取得することができます。その間雇用保険から「育児休業給付金」を受けることができますので、多くの方は引き続き「育児時短就業給付金」を受けるということになります。なお、「育児休業給付金」、「育児時短就業給付金」は男性も対象になります。
「育児時短就業給付金」の受給額は?
育児時短就業給付金の支給額 = 支給対象月に支払われた賃金額 × 10%
②支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90%超~100%未満の場合
育児時短就業給付金の支給額 = 支給対象月に支払われた賃金額 × 調整後の支給率
③支給対象月に支払われた賃金額と、(1)又は(2)による支給額の合計額が支給限度額を超える場合
育児時短就業給付金の支給額 = 支給限度額 - 支給対象月に支払われた賃金額
非常に分かりづらいですが、簡単に言えばその月に支払われた給与が以前の90%以下であればその月に支払われた給与の10%が支給されるということです。
育児短時間勤務制度を利用する方のほとんどは90%以下になりますので、上記のような計算が一般的になるかと思います。
従業員に子供が産まれると、出産前から出産後まで、企業として非常に多くの手続きをすることになります。それらの手続きは制度を正しく理解した上で、手続きをする時期もしっかりと管理する必要があります。
ほし社会保険労務士事務所では、顧問先従業員の出産前から出産後までの各種手続きを時期の管理までを含め全てお任せいただいております。
ぜひお気軽にご相談ください。